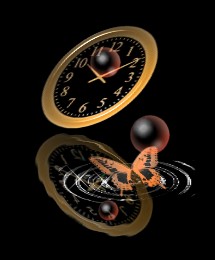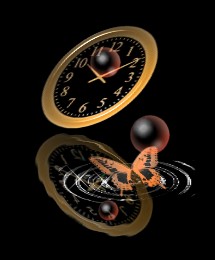よく喋る婆さんだと、アスマは内心呆れていた。
下忍を引き連れての呑気な任務帰りに行きあった腰の曲がった年寄りは、その曲がった背にあれもこれもと荷を積み上げ、杖をつきつつゆったりと目の前を歩いていたのだ。
ゆったりと――ではなく。
ゆっくりとしか歩けなかったのだろう。荷の重さ故に。
夕の陽がその背を寂しく照らし出していたなどと、どうして自分は思ったのだろうかと、今は自分の背にちんまりと納まった小柄な体に似合わぬ喋りっぷりに、いつも以上に無口になりそうだなと自嘲する。
「ばあちゃんチ、どこよ」
無口になったアスマの代わりとでもいうように、面倒くせぇと書いてある顔でシカマルが云う。その横に並ぶチョウジはお腹すいたとブツブツ云いつつも、重い荷のほとんどを負っていた。
「この先、坂よ」
アスマに背負ってもらって、おばあちゃんラッキーだったねと笑うイノに、それじゃあこっちはアンラッキーて奴だなぁと火の付いていない煙草を噛み締めたアスマは、ああだこうだと耳元でしゃべりまくる年寄りに適当に頷きを返しつつ歩を進めた。
老婆は、見た目以上に軽かった。
よくぞこの体であれだけの荷を負っていたものだと思わせるほどに。
だから語りというよりは呟きに近いだろう言葉の列に、黙って頷きを返してやった。
歳経た者のお決まりの台詞――近頃の若い者はという言葉の、その「若い」という分類に自分も入れられていると気付いてからは、多少は面倒くせぇとは思ったが。
若いと云われたってなぁと。
このガキ共から見れば、自分は充分おっさんでオヤジだろうと思う。
そういう基準で考えれば、確かにこの老婆から見たら自分はまだ若いかもなとも。
だったら背負って、荷物もついでとばかりに運んでやるのが、順当って奴だろう…
一日の半分を修行に、残りを任務にと費やした子供達は、アスマの目の前でまだ余力はあるのだと云いたげなほどには元気だった。風呂敷包みをぶら下げたシカマルも、年寄りにとっては大きすぎの行李を背負ったチョウジも、杖だけを持ったイノも。
そういやぁ背に負ったこの軽さはこのガキ共に似てやがるなと思い至った時に、ふと笑いがこみ上げてきた。
いつだったか、アスマなら軽々でしょとイノが背に張り付きチョウジが腰にへばり付き、仕方ねぇとばかりにそのまま歩き出した時のあの重み。シカマルはどうしたかと云えば、張り付くのも面倒だという顔をしていたので片手で掴み上げ肩に担いだような気がする。
お前等もうちっと食って体を作れやと云いたくなるほどの、完成されていない柔な軽い体。
早く一人前になれと思うと同時に、焦る必要もないと思ったものだった。それは何度下忍を受け持とうとも変わらない感覚だろうと理解していた。過度の期待は芽を潰す――だったら伸びるものは伸びるに任せ、貸せと差し出される手を引き上げてやるのが自分の務めなのだろうとも。
その按配がまた、面倒なのだが。
そういえばと、意味なくくわえていた煙草を放り投げる。それを文句を云いつつもイノが拾い上げたのに苦笑で返し、そういえば、一度だけ紅を背負った事もあったなと。
どの任務の時だと云えるほど確かな記憶ではない。少なくとも数年というほどは前ではないが、紅が上忍となった後という事は確かだ。
きっかけは足の怪我だったように思う。正直云って任務後の事だ、どうでもいいというのが本音だった。任務に支障を来すようなら半人前、支障無しで終われたならばそれで良し――少なくともアスマの頭の中ではそうなっている。
足がどうあれ当然のように勤めを果たした紅は、充分に好ましい忍だとその時に思ったものだ。唯一の不満はというと――頼れと、矛盾しているのは重々承知の上でだが、そう思えた事ぐらいだろうか。
任務が終わりを告げてあとは里に戻るだけとなったその時も、紅は足の事を云いも匂わせもしなかった。気付かれまいとしているらしいと知れたので、放っておこうと思い、とりあえず危ない事もなかろうとも思い――皆に遅れた紅に付き合ったのは別に同情ではなかったろう。では何なのかと今から思い返してみても、確とした回答は見出せないが。
大丈夫だと、常と変わらないのだろう顔で云われ、それじゃあいいかと先に歩を進める事ができるのならとっととそうしていたろうさと煙草を取り出した時、酷く非難がましい目で見られたのはよく覚えている。
そう、丁度イノが煙草臭いと顔をしかめて怒るのと同じノリで。
そしてその後――どうしたっけなと首を捻ろうとした時、皺の刻まれた手で髭を引っ張られた。
ここだよと、間断なく続いていたのだろうお喋りと同じ調子で素っ気無く告げられたのは、一軒の古びた家屋の前だった。青に近い紫の花が垣根に沿って植えられている事を除けば、古すぎて侘しげな。
ありがとうよと、はじめて礼の言葉を口にした老婆はアスマの背を降りて、乗り心地は悪か無かったねと呟きを落とす。続けて、荷を降ろそうとしているチョウジに向かって手を差し出して、疲れたろうから茶でも飲んでいけと。
報告を理由にそれを断ったのはアスマだったが――子供達は当然茶とそれに付随してくるであろう茶菓子に心を傾けていたようだった――あっさりとそうかいと向けられた背は、やはり寂しそうだと思った。
単に歳を重ねた者の持つ侘しさだったのかもしれないし、茜の暮れ時がそう思わせていたのかもしれない。どちらにせよ、ここは丁重にお断りすべき場面ではあるが。
そうかいと、あっさりと背を向けたはずの老婆は、じゃあこれを食べながら帰りなとシカマルの手にあった風呂敷包みから紙に包まれた饅頭を取り出して、子供の手に持たせた。当然それも、アスマは断るつもりだった。報酬を期待しての行動ではないのだと。誰にとっても他愛ない菓子の類であろうとも、けじめはけじめ。だから、折角だがと言葉を放とうとして――老婆がくしゃりと笑った。
こりゃあ年寄りの楽しみなんだよ、邪魔しないどくれ。
例えばそれが飴玉一つであったとしても、孫か曾孫かという子供相手に菓子を与えるのは年寄りの楽しみなのだと云われてしまえば、アスマもそれ以上は云えない。
それにしたって、甘い婆さんだと思う。この里の中で下忍となった子供を、未だ子供として扱うなど。もっとも、実際のところはまだ子供なのだが。イノもチョウジも、シカマルでさえも。
時折――ほんの時折、口元をゆるませたくなるほどには「らしく」振舞う事はあるのだが。
「ありがとう」
いつもの小生意気な顔でなく、歳相応の子供の顔で礼を云うイノ達にくるりと背を向け、行くぞと気配だけで伝えると、ベストの裾を掴んで引っ張る手があった。今度は何だと手の主たる年寄りを振り返ると、ずいっと青の塊を鼻先に突きつけられる。
青の塊――垣根のあたりに植わっていた花を。
あんたにゃ饅頭よりゃ酒だろうが、今日はいい月みたいだからね、これを肴に一杯やるのも風流ってもんだよ。
云うその顔は柔らかさに染められていた。もみしだかれた落ち葉の如き柔らかさだ。
「あ、ねぇ先生、それ私にも少し頂戴、桔梗って好きなのよ」
イノの言葉に、ああこれは桔梗だったなと今更のようにアスマは気付いた。
深い藍の色の、凛と立つ花だと。
そして唐突に思いだした。あの時――紅を背負ったと記憶が告げるあの時、結局背負ってやろうという言葉をいえなかった事を。
紅は一人で立ち、歩いていたのだ。危なげない足取りで、凛と立っていたのだ。
自分がしてやるべき事は、手を貸す事でも背を貸す事でもないのだと、その姿に思ったのだ。
だから並んで、ただ歩いた。
早く戻って一杯やりたいんじゃないのというご尤もな言葉に、煙草に火を付けるだけを返答として、歩いた。真っすぐに里目指して、傷めた足に負担をかけぬよう、ゆっくりと…
何で俺は、あの時あいつを背負ってやったと思っていたのだろうかと、イノの手がきっかり半分の桔梗の花を手から奪っていくのを眺めつつ考え出したアスマは、ただ面倒くせぇなと髭を撫でた。
記憶の取り違えなどめったにある事でもあるまいに。
「あのおばあちゃん、生け花得意なんだって、暇だから教えてくれるって」
家に戻れば腐るほど花があるというのに、人からもらった花というのは格別嬉しいのか、イノは半分崩れた門の前で見送っている老婆に何度も手を振っていた。何時の間にか自分の分だと手にした桔梗はリボンで括られている。貰った饅頭はあんたが一番重たいの持ったんだからあげると、チョウジの胃袋に納まっていたらしい。
「雨でも降るんじゃねぇ?」
イノがチョウジに食い物譲るなんてよと、シカマルは僅かばかり口の端を上げていた。何とでも云えと、貰った花を満足気に眺めるイノは、この色合いがいいのよとただ笑っている。地味なんだけど、この時期になるとついつい飾っちゃうのよねぇと。
花なんか飾っても食べられないじゃないかというチョウジのぼやきに呆れた声を上げようとしたイノの頭に手をおいて、急ぐぞと告げたアスマは桔梗と同じ色に染まりだした道の向こうに目を向けた――
任務報告を提出している間中、早く帰ってご飯にしたいと煩くまとわりつく子供を適当にいなしつつ、手にした桔梗をどうしたものかとアスマは考えていた。貰ったものを捨てるなど考えられず、といって自分が持って帰るなどもっと考えにくい。イノにおしつけてやろうと思ったものの、桔梗っていうのはちょっとだけ飾るのがいいのよと返される始末。
やっぱり髭に花なんて似合わないわよねぇと、笑われたが。
「随分と遅かったのね」
静かな声が傍らからかかり、そこに先程まで思い出していた紅の姿を認めてアスマは苦笑した。ちぃっとな、予定外って奴よ。いつものこったろうと言外に匂わせてやると、自分流に解釈したのだろう、紅はそれ以上は云わずに報告書を提出した。
その姿をちらりと眺めて――伸びた背筋に、やはりあの夜を思いだす。
一人で立てると全身で告げていた、あの時を。
そして、ああと納得するのだ。
手を貸してやろうと思い、面倒だから背負って帰ろうと思ったあの時、自分は伸ばされた紅の背をそのままにしておきたかったのだと。
凛と立つ、その姿こそが好ましいと。
触れてみたいと思う以上に――
そうか、自分は背負ってやりたかったのではなく、背負いたかった――触れたかったのだと、アスマは奇妙に納得したのだ。だからそこに、記憶のすり替えが生じたのだと。
あの頃の紅はまだ、遠かったのだ。実質的な距離も、感覚的な距離も。
その距離を感じ取っていた自分もまた、紅から見たなら遠かったに違いないと思うアスマは、それが今じゃどうだろうと下忍達に明日の指示を与える紅の後姿を眺めやった。伸ばされた背はそのままだが、そこには僅かながら余裕が感じ取れると。
それでも――一人で立っていられるのだと、未だ背は告げているのも事実だが。
そりゃそうだ、そうしねぇと生き残れない世界だからなぁ…
がりがりと頭を掻いて早く帰りたいと目でも口でも告げてくる子供達に明日もいつも通りになと、これまたいつも通りの言葉を与えて解散させると、アスマは紅の目の前に桔梗を指し出してやった。貰いモンだがと前置きし。
一瞬怪訝そうな顔をした紅だったが、そんな季節になったのねと密やかな笑みを口の端にのぼせた。月に良く映えそうだとも云って。
「これに似合いのお酒がある飲み屋なら、知っているわ」
花を見たまま云う紅の声が幾分柔らかい事に気付いたアスマは、火をつけかけた煙草を手の中でくしゃりと丸め、食いモンも旨けりゃいいなと戸口へ足を向けた。わざとゆっくり歩を進めると、追いついた紅が横に並んだ。前でも後ろでもなく、隣に。それが当たり前であるかのように。
「月見酒になるのかしらね、それとも花見酒?」
お前の好きにしたらいいだろう。云いかけた言葉を飲み込んで、さてなぁと新しい煙草をくわえたアスマに、紅はマッチを箱ごと差し出した。
「桔梗のお礼」
云う紅の唇が、藍の桔梗と相まってより鮮やかだと思った事を、アスマは自分の裡に沈める――
言葉に違わず旨い酒を流し込みつつアスマは紅の背後に見える月を眺め。
辛口の喉越しの良さに満足げな笑みを浮かべる紅は地味な花に目線を送り。
賑やかな飲み屋の窓辺の席で、言葉少なく杯を重ねる二人の間に活けられた桔梗は、声にならない言葉に耳を傾けるようにひっそりと揺れた…
|