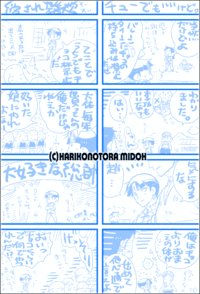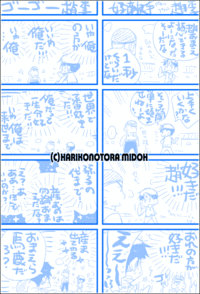R18
さすがに今回は、
やりすぎじゃ、ねえのか、と。
小狭な浴場で椅子に座り、向かい合って抱き合いながら、李功は揺れに度々言葉を奪われつつ、埒もない感想を漏らした。
夜が明けた頃、李功が本格的に眠りから覚醒する前に起床し、汚れものを脇に抱えて早々に洗濯を行うべく部屋を出た。
風呂の湯を沸かしながら、その傍らで下着や服を踏み洗いで洗浄していたのだが、いつまで経っても相手が起きる気配がなかったので寝室まで迎えに行くと、すでに李功はベッドの端に腰かけ、白い首を傾げていた。
服はどこへやったんだ、と堂々と足を開いたまま股間を隠しもせずに訊いてきた黒い頭に、洗い終わったから干しているところだと告げると、途端に柳眉を大きく歪ませた。
しかしすぐに思い直したのか(そこが李功のいいところなのだが)、背後を振り返り、もうひと眠りすればいいかと思考を軌道修正したようだ。
そんなわけがあるか、と嘆息しながら上腕を掴んで立ち上がらせると、面白いように膝を崩してきた。
咄嗟に体と腕を使って支えると、あー悪い、と気の抜けたような声が届いた。
まだ本調子ではないのだということを察し、さすがに盛りのついた動物のように一晩中励んでしまったことを後悔するところだったが、風呂の用意ができていると告げると何とか自力で立つことができたようだ。
下手をすると再び女のように抱き上げられて連れて行かれると懸念でもしたのかもしれない。
身体を洗ってやる、と言うと、やはりというか、李功は何とも言えない顔つきになった。
元々、身内の世話を焼くことそのものを苦労と感じることが少ない体質だった。
特になぜか、恐らく好いた相手だけに限ってなのだろうが、事後の汚れた肌を拭ったり、髪を梳き衣服を着せて整えてやることがごく自然にできているという自覚がある。
苦ではない、というのが本来的確な表現で、義務という認識が強く、決して好んでというわけではない。
李功は李功でやりたいようにさせているのだが、当初はなんでこんなことまでするんだ、と明らかに眉をひそめていた様を思い返す。
こどもじゃねえんだぞ、と断られたことも現にあったが、だからどうした、と視線で訴えると、それ以降不満を言わなくなった。
過度の奉仕精神や、他者の身体を自由に扱うのが好きなのではなく、こちらがしたいようにしているだけだと悟ったためだろう。
議論するだけ無駄であると察したからこその賢い選択だったのだろう。
李功が自分でやるといっても、結合していた余韻が強過ぎる時は腰はおろか手指にも力が入らないことが多かったので、結果オーライだ。
それに今回は、他に目的がある。
「どうせ奥まで届かないんだろ?」
「…………………………」
聞くなり、李功は憮然とした。
どこを指しているのかを一発で的中させたからこその反応だった。
昨夜、数週間、練りに練り続けた濃い精を李功の体の一番奥に放ったのは、故意だ。
なぜなら、欲望に理性を貪り食われても、よほどのことがない限り意図しない射精を行うことは皆無だからだ。
そうだと言い切れるのは自負であり、自戒のようなもので、白華の師範を務めているという矜持にも関わる。
それは李功とて同様で、無理矢理快感を引き出すような拷問を実際に受けたとしても、そう易々と体外に種を放出するような無様を晒すことはないだろう。
今更説く必要もないほどに、高ランクの拳士として内外のエネルギーを操る術を体得している所以だ。
「体くらい、自分で洗えるぜ」
「ああ。…じゃあ、見ててやる」
目的の場所まで届いているのかどうかを。
「……………………………………」
相手を睨みつけながら黙り込んだ李功の顔が赤面しているのは、恥じらいのためか怒りのためなのかの判別は付きそうで付かなかった。
そうしてると、黒龍拳の総帥も形無しだな、と思わなくもない。
どんな悪趣味なんだよ、と李功は歪めた唇で悪態をついたが、ぐいぐいと強引な力でこちらに流されることにはすでに慣れてしまっていたのだろう。
反論のしようがなかったのか、舌打ちとともに項垂れ、覚悟を決めたようだ。
しかし道の先頭は譲らず、強がって前を行く。
全裸であることはもはや当人にとって問題ではないらしい。
後方でうっすらと苦笑を浮かべながら、李功の後に続いて風呂場へ足を踏み入れた。
泡立てた海綿を使って、早速李功は爪先から頭の天辺まで拭いきったようだ。
相変わらず異様なまでの手際のよさだと思ったが、見られているからこそのスピードだったのかもしれない。
表面にシャボンが付いたままであるとはいえ、もう一度洗い直してやるつもりで傍らに立つと、みぞおちに使い終わった海綿を押しつけられた。
先ほどまで履いていた下衣は脱いで、勿論自身も一糸まとわぬ姿になっている。
「…おれはもう済んでる」
受け取った物を水を張った桶の中に放り、あとは湯に浸かるだけだと明かすと、李功は無意識だろう、唇を噛んだ。
「………教えてくれるだけでいい」
「………………………」
後ろの洗い方だけ教えてくれれば事は足りるとの主張だが。
初めて李功の中に出した前回は、自らの不徳のために不本意にも喧嘩別れのような形になってしまったが、その時はといえば想像しなくても李功自身の手で片付けたのだろう。
しかし今丁寧に教えてやろうと思った理由は、先回の後ろめたさがあったためと、それから。
臀部の割れ目に指を這わせる相手の痴態を見てみたかったなどと白状できるはずもない。
立ったまま無言で濡れた腰を引き寄せる。
上から覗き込むようにしながら、李功の後ろへ背後から手を這わせた。
膨らんだ丸みの間に潜んだ一点に中指の腹を当てると、李功が息を詰めた。
相手の挙動は、夜であっても朝であってもさほど変わらない。
陽の光が差し込んでいようといまいと、強がる姿勢に変化はない。
意地っ張りのように映るが、単に生まれ持った気同様、意思も強いだけなのだろう。
だからこそその鼻っ柱を折ってみたくなるのだという反骨の精神は、ひとまず今は封印しておく。
ここだ、と教えるようにして数回表面を撫で、その指を持ってくるように促す。
決心したのか、早くこの作業を終わらせてしまいたかったのか、一瞬も躊躇せずに李功は手を伸ばしてきた。
振り返るような恰好で鍛えられた左腕を伸ばす。
押さえていた温もりの位置を交代するように場所を譲ると、躊躇わずにそこに押し入ったようだ。
自分が触れる時よりも、李功の反射は穏やかだ。
何がどう動くのかを知っているからこその手ごたえだったが、集中してしまえばこちらの目など気にならなくなるらしい。
近距離で見つめている側はといえば、そんな冷静なことも言っていられないが。
少しずつ、少しずつ、深く、深く。
「………っ………」
李功の呼吸が跳ねたのを認め、噤んでいた口元に力を入れた。
そうさせたのは間違いなく、次第に重くなる下肢が原因だったのだろう。
「…………………」
断りもせず、手に手を添える。
「……!!!」
前触れもなく狭い内側に自分と親友の二本分の体積を受け入れる事態に陥り、ぐ、と李功の喉が鳴った。
まさかいきなりこの場面で他人の介入があるとは予想していなかったのだろう。
振りほどこうにも手の甲の上から押さえられているので、密着した状態から抜け出すこともできない。
「いいから、このまま……」
このまま黙っていろ、と強い視線で命じ、すぐに李功が辿った距離まで至る。
懸命に乱れかける呼吸を正常値まで引き戻し、真摯な態度を取ることで李功に警戒させないよう努めた。
つい数時間前にも、おのれの触覚器官や局所で味わっていたはずの密な空間を進む。
内部の熱が高まっていくのを皮膚の上から感じながら、この先だと見当を付け、さらに奥へ先端を伸ばした。
李功の背が撓り、後頭部が肩を突いた。
視線がかち合った拍子に堪らず上方からその口端に口付けた。
しかしこれでは汚れを洗っているのではなくただの性交だ、と自らを叱咤し、すぐに離れる。
李功の奥を先っぽで撫でさすり、泥濘のような感触を感じた部分でわざと壁を突くように節を曲げた。
っ、と、ひるんだような声音が耳に届く。
「…………ここだな」
ぬるついた箇所を畳み掛けるように指で捏ねると、さらにびくびくと李功の太股が痙攣した。
執拗な愛撫に立っていられなくなったのか、右腕がこちらの脇に回る。
縋るような媚態に脳髄をぞくぞくと痺れさせながら、飽くまで平静を装った。
「拡げるぞ…?」
内股を伝って流れ出した分については夜の間に拭いとってしまったが、微量の残滓がいまだに李功の直腸に居座っていることを確認し、反対側を押すよう促した。
ここに自身の指が二本入っていれば同時にその隙間を押し開くことが可能なのだが、残念ながら自分と李功の一本ずつしかない。
どんな共同作業だよ、と相手の心の声が聞こえてきたが、無視して顎でしゃくり、重ねて命じる。
わずかに顔を背けながら、李功は言われた通り自身の指でそこを広げた。
事が終わり抜き出す前、向こうが要らないと言うのも聞かずに、内にある李功の性感帯のひとつを教えてやった。
ここを弄れば好くなる、と。
大きなお世話であることは明らかだったが、自慰の時に後ろを使うなら知っていた方が何かと都合がいいだろう。
どんな親切なんだよ、と李功はあからさまに声を荒げたが、おれのことを考えながらしてほしいからだ、と気真面目に返答すると、諦めたように瞑目して天を仰いだ。
それを肯定と受け取り、いつも欲しがるところを繰り返し突いてやる。
ゆっくり、撫でるように。
次いで、激しくぐりぐりと押しつけるようにして刺激する。
李功の下半身が揺れ、前が明確な形を持って持ち上がってくる様子を視界に収めながら、押し留めていた自らの呼気を盛大にならない程度の遠慮を伴って吐き出した。
「………好いだろ…?…」
李功、と赤く染まった耳元で囁くと、目を瞑ったまま、ああ、と短く応答が返った。
粘膜の筒の中でともに濡れている李功の指を再度導き、動きを倣わせ、数度。
動かした瞬間、唇を噛みしめ、前傾した。
床の上に倒れ込んでしまわないよう、引き締まった腹部に腕を回してさらに支える。
背後で密着した背骨に覚えのあるものの硬直を感じ、正体を悟ったのだろう。
趙(しょう)、と、音にはしなかったが、流し眼とともにこちらの顔を見上げてくる。
その普段とは似ても似つかないような純朴とも思える仕草を見て、堪え切れず笑い出してしまえば、もう出て行けよ、と弱音を吐いた。
そんな心にもないことを言うな、と相貌の下半分を歪ませて応える。
今のおれは白華の師範失格だな、という自嘲を込めて。
「……二人でやれば、もっと効率がいいぜ……?」
単独で事後処理を行うよりも、一緒に励めば双方に利益があるだろう、と。
尤もらしい口説き文句だったが、淫猥な響きが含まれているのは否定できない。
だったら、早く、しろ、よ、と。
素肌を紅潮させ、汗と水で乱れた前髪の李功が困ったように唇を突き出して訴えた。
それから、現在に至る。
最初のうちは半分までと決めて注挿を繰り返していたのだが。
結局は李功に強請られ、根元まで。
この方が奥まで洗えるだろう、と切れ切れに発された向こうの提案の正否の判断は別として。
浴場に設えられていた腰かけに座り、前から李功の全身を抱き込むようにして繋がった。
目線を真下へ落とせば、李功の丸い臀部の奥様で繋がっている雄の象徴を一望することができる。
旨そうに太い幹からその付け根に至るまで、すっかり銜えこまれている光景は、卑猥という他はない。
相手の膝裏に腕を差し込み、五体を掬い上げるようにして結合しているので、李功にとっては不安定だろうに体格の大きな差によって不思議と安定した。
すっぽりと李功を抱き込んだ体勢で、首の後ろに相手から回された腕を感じ。
目の前の体と密着し、敏感な部分をおかし、揺さぶり、心地好さを引き出すように腰を使い、抱く。
深く穿ち、一方は受け入れながら、正面から互いのあからさまな表情が覗けるので、正に今、一分の隙もなく利害が一致しているのは疑う余地もない。
時々両方の額を擦り合わせ、物欲しげな口をどちらからともなく塞ぎ合ったり、口腔から食み出す分厚い舌を舐め合ったり、絡め合ったり。
そうして飽きもせず、当事者以外誰もいない室内で蜜月の続きを耽溺した。
はずだった、のだが。
「おはようございます」
洗濯物を取り込むために表へ出た途端だった。
反射的にぎょっとして振り返った先には、ティッシュボックスを脇に抱えた、潰れ顔の男の師範。
寝不足なのか、擦った目は白兎のように赤く腫れている。
なんでここに知り合いがいるんだ、と怪訝に思う暇もなく、智光(ちこう)はなぜか慇懃に両手を合わせ、こちらに寝癖のついたこうべを垂れてきた。
それもそのはず。
続いた呼称は、思わず目を丸くしたまま顔面を茹で上がらせたくなるようなものだった。
自身を前に礼儀正しく腰を折り。
「ペニスマスター(先生)」
次に、後から扉を開けて出てきた李功に向きを変え。
「アヌスマスター」
どっと、李功が地面に背中を付いて倒れ込んだのは言うまでもない。
(ずっと最後のシーンを書きたかったとは口が裂けても言えません)